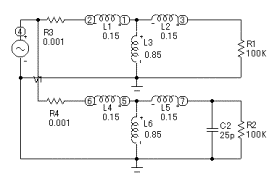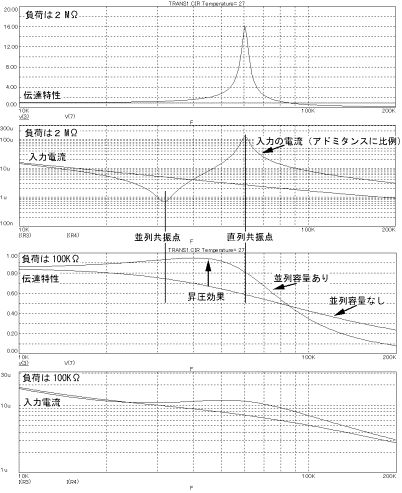2001.12.10 株式会社テクノリウム 牛嶋 昌和 回路シミュレータにより直列共振による昇圧効果のシミュレーションを行なった。 1.回路シミュレータ 用いたシミュレータ Micro-Cap Ⅴ/CQ判 2. 被告乙7号証の検証
被告は準備書面(2)の中で、直列共振点とは位相の0degでなければならないと述べているが、それは、被告乙第2号証の2「イラストで電気のことがわかる本」表紙172ないし175項第で示されるように、抵抗成分RがL・C素子と直列に接続されている直列共振回路の場合だけであり、本件のように、共振回路を構成する素子の一方に並列に抵抗Rが接続されるような例では、直列共振回路構成であっても力率最良点(0deg)と共振頂点は必ずしも一致しない。力率最良点は直列共振周波数よりも少し低い周波数になる。 被告提示の直列共振回路(乙7号証同図4b)に基づいて検証した結果においても、本件特許の重要な効果である、直列共振回路による昇圧効果と、直列共振付近の力率改善効果のそれぞれを確認することができた。 3. 被告乙第7号証に並列共振成分を加えた検討
三端子等価回路に代入するそれぞれのインダクタの値は以下の式により求めた。
図5-5は、上から伝達特性、入力電流(アドミタンスに比例)、位相特性である。 並列成分の追加により、次のような結果が得られた。
などの性質も再現され、このシミュレーション結果はより実態に近いものであることは明らかである。 まとめ 直列共振による力率改善効果は直列共振の働きによって、直列共振頂点よりも少し低い周波数に発生する。 また、昇圧効果や、力率改善効果は並列成分を追加した後も直列共振点付近に生じることは、直列共振のみをシミュレーションした図5-3の結果と基本的に変わることがなく、並列共振成分は、本件特許の持つ効果を滅失するものではないことが確認できる。 したがって、直並列負荷共振(SPLR)の直列共振成分は本件特許明細書の、直列共振と等価である。 4. 直列共振の昇圧効果について 本件特許は明細書【0010】「チョークコイルの誘導成分を二次側回路に生じる寄生容量またはこれと並列に接続された補助容量によって打ち消してやることにより直列共振回路を構成し、放電管に高い放電電圧を給電する」ものであり、この効果をシミュレーションにより確認する。 (1) 等価回路 このシミュレーションの目的は、並列容量のある場合とない場合について、伝達特性(トランスの昇圧効果)を比べたものである。 図5-7の結果は図5-6の等価回路により並列容量のある場合とない場合について、伝達特性を比べた。
図13-6の等価回路により図13-7の結果が得られた。 R1、及びR2に発生する電圧、R3、R4を流れる電流についてシミュレーションを行なった。 上の二つの図は並列共振点と直列共振点を明確にするため開放状態(R1及びR2を2MΩ)にして並列共振点、及び直列共振点を計ったものである。 下の二つの図は6mAにおける冷陰極管の等価抵抗を約100KΩとして、並列容量がある場合とない場合の伝達特性の比を測定したものである。
(2) 結果 被告主張によれば被告製品のトランスは漏洩磁束性が少ないのであるから、実用とされる周波数において しかし、シミュレーション結果によれば並列容量がない場合、放電管(抵抗R1、R2)の両端に発生する電圧は約30%以上低下している。 このようなことから見ても被告製品のトランスは漏洩磁束型である、或いはトランスの漏洩磁束性を利用して使っていることは明白である。 並列容量が存在することによって、この低下した電圧を「並列に接続された補助容量によって打ち消して」いる様子が現れている。 また、共振による昇圧効果が最大となる周波数は直列共振点よりも少し低い周波数に発生していることも示されており、本件特許の効果が直列共振点の頂点に限るものではないこともまた明白である。 さらに別の角度から並列容量による効果を検討すれば次のようになる。 被告乙第6号証の測定結果のうち二次換算漏れインダクタンスLts(JIS C 5321標記Ls)の値256.7mHが正しいと仮定すれば、液晶パネルの冷陰極管の6mA時のインピーダンス(抵抗成分)は91KΩであるから、Ltsのリアクタンスが91KΩになる周波数(ターンオフ周波数)を求めることができる。 したがって、被告製品のインバータは56.4KHzにおいて、トランスの漏洩磁束性がない場合の本来の昇圧比に比べて (なお、この計算値は乙第6号証の正確な再測定を待って再計算を行ないたい。) この30%の電圧低下を並列に接続された容量が補うのである。 この30%の電圧低下というのは冷陰極管の点灯にとっては致命的な意味を持つ。 なぜならば、甲19号証P14一段最下行「しかし、ある程度まで電流が流れると、電圧の減少はゆるやかになり、図1のようにほぼ定電圧特性を示します。」の記述、及び、甲5号証図11及び図12冷陰極管VI特性に示すように、冷陰極管の点灯電圧は実用域でほぼ一定なのであるから、放電電圧が僅かに変化するだけで管電流が大きく変化する。また放電電圧が僅かに不足するだけで不点灯になる。 したがって、並列容量が存在することで共振し、それによって起きる電圧の上昇効果は冷陰極管の点灯にとって実に重要なものである。 なお、被告は本件特許の直列共振について、インバータを直列共振頂上において動作させることであると主張しているが、本件特許明細書に述べる昇圧効果は直列共振周波数頂上よりも低い周波数に生じており、本件特許技術に基づくインバータ回路は直列共振点頂上における動作を意味しているものではない。(参考資料2,3に対する反論) また、被告は参考資料1において、甲17号証図4の中で「アドミタンスから見た極大値は原告主張の65KHz近辺にはなく・・・」と述べているが、シミュレーショングラフ図5-7を見てもわかるように、蛍光管インピーダンス(図5-6R1,R2に該当)が低くなると共振がダンプされて見えにくくなるだけのことであり、共振点がなくなるわけではない。(並列抵抗R1が2MΩの場合、直列-並列共振点がはっきり観測されるが、R1を100KΩとすると、直列-並列共振点は非常に見づらい。この様子は図5-5でも表れている。) 甲17号証図4に5mAの測定結果と同時に3mAの測定結果も示したのは、管電流が少なくなると冷陰極管等価抵抗値が高くなるために、アドミタンス極大点がより明確にわかるため比較のために示したものである。 3mAの図によれば、アドミタンス極大点(直列共振点)が60KHzであることは明白である。 | ||||||||||||||||||||||||||
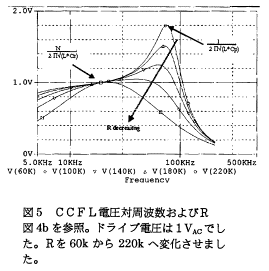
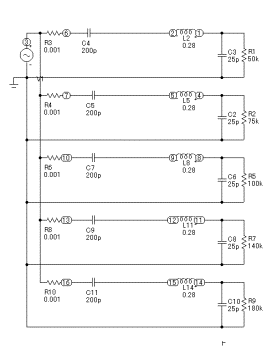
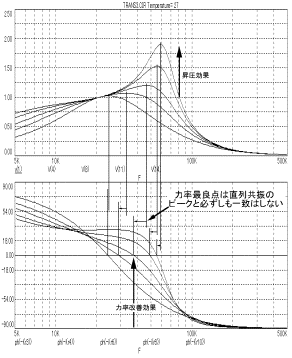
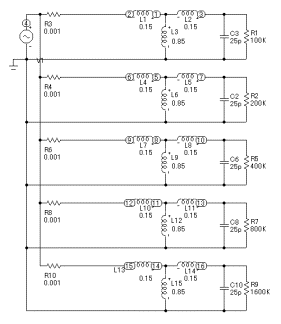
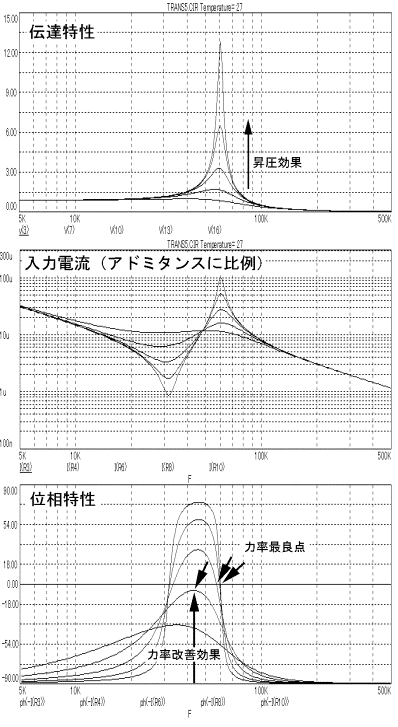
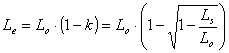 だから、
だから、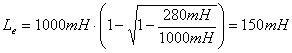 および
および